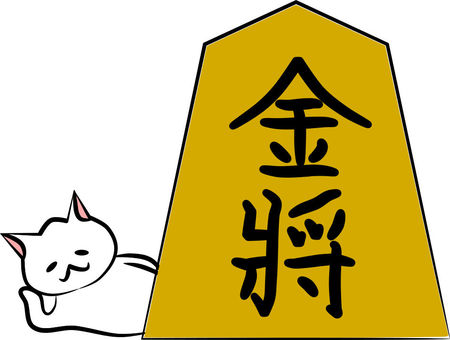疲労感はマスキングできてしまう
痛みや熱と違って、疲労については無視したり軽視したりする人がとても多いです。
私たちが疲労感を無視してしまう1つの要因は、疲労感を一時的に「マスキング」できてしまうことです。
マスキングとは上から覆い隠すことをいいます。使命感や仕事のやりがい、褒賞への期待、あるいは「ここでがんばらなければみんなに迷惑をかけてしまう」という責任感などによって、疲労感を覆い隠すことができるのです。
ものすごく疲れているときでも、「今度の大会で一等賞をとれば、欲しいものを何でもプレゼントするよ」といわれたらどうでしょう。賞品に釣られて疲れを感じないことが実際にあると思います。
疲労感を一時的に忘れることができるのは、脳の発達した人間がもつ、すばらしい能力ではあります。一時的にがんばらなければならないとき、どうしても責任を果たさなければいけないとき、この能力があることによって私たちは急場をしのぐことができます。
問題は疲労感のマスキングを恒常的に繰り返してしまうことです。
自分が疲れていることを認めず、十分な休養をとらずに活動を続けていると、今度は少し休んだくらいでは疲れが回復しなくなります。疲労の蓄積の始まりです。こうなると疲労が回復するまで、予想以上に時間がかかります。あるいは本当に病気になってしまうこともあります。
マスキングし続けた先には「バーンアウト」が待っている

疲れ方というのは、個人差が非常に大きいものです。
どのくらい一時しのぎができるかはその人の年齢や体調にもよります。
「あの人ががんばれるのだから、自分も同じようにがんばれるはず」ということはありません。それにもかかわらず疲労感をマスキングし続けることは、体にとって相当な嫌がらせになります。
人それぞれ、もって生まれた体質は違います。
睡眠時間も同じで、3時間でも大丈夫な人と、10時間寝なければダメな人がいます。仮に年齢や性別が同じでも、体質は一人ひとり違うのです。
人間は永遠にがんばり続けることはできません。マスキングが常態化してしまうと、どこかでポキッと折れてしまうでしょう。
その先は「燃え尽き症候群(バーンアウト)」と呼ばれる状態になることが知られています。
燃え尽き症候群には12段階があり、最初は自分の存在価値をなんとか証明しようと一生懸命無理をすることから始まります。次に「がんばる」とか「ひきこもる」などの段階を経て、11段階目になると、うつ病になります。最後が燃え尽き症候群です。
こうなると何もできない状態になってしまい、治療に時間を要することになります。
あえて自分に負荷をかけてみる

じつは、活力を高めるには、あえて自分に何か負荷をかけることがポイントです。
「疲れが取れきっていないのに、もっと疲れることをするなんて、とんでもない」
そう思うかもしれません。しかし適切な負荷をかけたあとにもう一度しっかりと休養の時間をとると、ストレスをかける前よりも体力がつくことになるのです
もとの体力が10だとすれば、あえて負荷をかけることで一時的にパフォーマンスが7や8に落ちても、回復時には体力が11になっている。
そして次の休日にまた同じことをすれば、回復するころには体力は12になっている。こうして基礎体力が徐々に上がってきます。
もちろん現時点で疲弊しきっているならば、まずはいったん疲労をゼロに近づけるようにすることが先決です。それ以上の負荷をかけたらそれこそ大変な負荷になってしうので、いきなり無理はしないでください。
疲れが残っているけれど多少は余裕があるなというときや、まだ疲れが取りきれていないけれど少しは何かやってみてもいいと感じたら、軽い負荷をかけてみてください。それから十分に休養するのです。
疲れたら、休みつつ、負荷をかける。これが活力を高めるうえでのポイントです。休養だけでは50%程度しか充電できなくても、活力を加えて満充電に近いところまでもっていけるのです。
活力を高める上手な負荷のかけ方がある

負荷といっても、最初は軽いものから始めます。
また、次の4つの条件を満たすことが必要です。
1.自分で決めた負荷であること
誰かに「やりなさい」と押しつけられたものではなく、自分で決めることが重要です。押しつけられたものだと、それがまた別のストレスになってしまいます。
2.仕事とは関係ない負荷であること
仕事で疲れているのに、さらに仕事で負荷を増やすのはおすすめできません。家族から「日曜大工で家具をつくってほしい」とリクエストされていたけれど、面倒くさくて逃げ回っていたことはありませんか。こうしたものは仕事と関係がありませんから、負荷としては最適です。
3.それに挑戦することで、自分が成長できるような負荷であること
分厚い本を読破する、地域活動で何かの係を引き受けるなど、「ちょっと難しいけれど、これができたら自分は成長するだろうな」というものに挑戦してみることも、よい負荷です。
4.楽しむ余裕があること
くれぐれも無理は禁物です。
楽しめる範囲内で負荷をかけましょう。
さらに、自分に負荷をかける課題は、できれば肉体的なものと精神的なものの両方があるといいでしょう。
肉体的な負荷なら、最初は軽い運動から始めてみます。
ウォーキングをすると決めたら、楽しみながら距離を延ばしていき、ゆくゆくはランニングに移行する、という感じです。自分でペース配分することが可能なので、負荷としてちょうどいいと思います。
一方で精神的な負荷についても少しずつかけていくといいでしょう。
難しい試験にチャレンジしたり、趣味の世界で何かの賞に応募したり、山登りで百名山制覇を目指したり。こうしたポジティブな負荷を課してみることが大切です。
これから疲れそうだから、先に休んでおく

理想をいうと、長期休暇は繁忙期の前にとるとよいと思います。十分に休養と活力を得た状態で、仕事のピークに突入できるからです。
この先どんな活動をして疲労するかを予見して、それに必要なエネルギーである活力をためておくのです。
疲労したから休むのではなく、疲労しそうだから先に休んでおく、といってもいいでしょう。
これは長期休暇に限ったことではなく、毎日・毎週のスケジュール管理にもいえる話です。
「明日は子どもと一緒に公園に行って、そのあと食料品の買い出しにも行くから、たぶんすごく疲れるな。今日は早く寝て、エネルギーを蓄えておこう」
「今週はデスクワークが中心だから、それほど体力は消耗しないだろう。エネルギーはそんなに必要ないかもしれないな」
こんなふうに、予定される活動から逆算して、必要な活力を蓄えておくという発想に、ぜひ、切り替えてみてください。