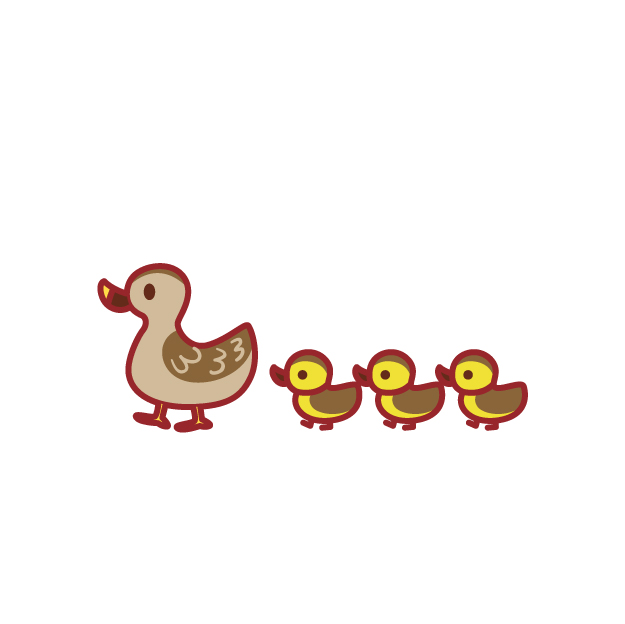朝、リビングで立ち尽くしながら「何を取りに来たんだっけ…」と考え込む――50代の友人が話してくれた、ちょっとした物忘れのエピソードです。誰にでもあることですが、ふと「もしかして認知症の始まり?」と不安になる瞬間ですよね。
でも、心配しすぎることはありません!認知症は早い段階から生活習慣を整えることで予防の可能性が高まる病気。50歳から始める小さな工夫が、未来の自分の心と暮らしを守る力になります。
認知症になるメカニズムと認知症対策を知って、みなさん、健康寿命をもっともっと延ばしましょう!
– 目次 –
どうして認知症になるの?そのメカニズム
認知機能が低下する要因とは
認知症を予防するために
1. 体を動かす習慣をつけましょう
2. 脳を活性化させましょう
3. 人との交流を大切に、社会とつながりましょう
4.食習慣の改善も大切です
不安な時は早めに相談しよう
どうして認知症になるの?そのメカニズム
認知症は、一つの病気ではなく、様々な原因で脳の働きが低下し、その結果、日常生活に支障をきたす状態の総称です。代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、血管性認知症などがあります。
私たちの認知機能は50歳を過ぎた頃から緩やかに低下し始め、60歳を過ぎるとその低下が加速することが分かっています。
特に95歳を過ぎると、脳の機能低下はさらに著しくなります。これは、物事を記憶する力や注意する力、判断する力などに影響を及ぼします。
アルツハイマー型認知症の主な原因の一つは、脳の中に「アミロイドβ(Aβ)」という異常なたんぱく質が少しずつ溜まっていくことだと考えられています。このアミロイドβの蓄積が進むと、別の「タウたんぱく質」というものも異常になり、結果として認知機能の低下が進んで認知症へとつながると言われています。
認知機能が低下する要因とは

認知機能の低下には、以下の要因がいくつか複雑に絡み合っています。
認知症は初期の物忘れから始まります。徐々に時間や場所の認識が難しくなったり、日々の家事や仕事ができなくなったりと、段階的に症状が進んでいくのが特徴です。重症度は「軽度」「中等度」「重度」に分けられて診断されます。
生活習慣病
高血圧や糖尿病といった生活習慣病は、認知機能の低下に影響を与える可能性があります。
身体活動の低下
年齢を重ねると、体を動かす機会や人との交流が減りがちです。これにより、脳への刺激が少なくなると、脳の萎縮が進み、認知機能の低下が加速してしまうことがあります。特に、筋肉量が減る「サルコペニア」や、心身が虚弱になる「フレイル」の状態は、活動量の減少や転倒のリスクを高め、結果として脳への刺激不足から認知症の進行を早める要因となります。
環境や社会とのつながり
周囲からの刺激が少なかったり、人との交流が乏しく「社会的に孤立したりする」ことも、認知機能の低下を加速させ、認知症やうつ病のリスクを高める要因となります。
認知症を予防するために

認知症の予防には、「早めの対策」と「日々の生活習慣の改善」がとても大切です。
特に、50代以降は、今後の人生を健康に過ごすために、今からできることを積極的に取り入れることが鍵となります。
予防方法は、主に以下の4つの柱に分けられます。
1. 体を動かす習慣をつけましょう

適度な運動は、認知症の予防に大変有効です。50歳以降は、筋力だけでなく、柔軟性、バランス、そして認知機能の全てを維持することが非常に重要です。
筋力トレーニングで筋力を維持
筋力トレーニングは、認知機能の改善に著しい効果があることが報告されています。筋肉を鍛えることは、上で述べたサルコペニアやフレイルの予防・改善にもつながり、結果的に認知症のリスクを減らす助けになります。
筋トレを始めるのに遅すぎることはありません。80代、90代になっても筋力トレーニングやウォーキングを継続することは、身体的・精神的な健康を保つために極めて重要です。今からコツコツと続けることが、将来の健康につながります。
有酸素運動は脳を活性化する
ウォーキングのような有酸素運動は、脳を活性化させ、新しい神経細胞が作られるのを促す効果が期待できます。
柔軟性とバランスを整えて転倒を予防
関節の柔軟性を保つためのストレッチ運動や、転倒を防ぐためのバランス運動も大切です。転倒は、活動量の低下や怪我につながり、認知機能の低下を加速させる原因となることがあります。
生活の中で体を動かそう
日常生活の中で、できるだけ体を動かす工夫をしてみましょう。例えば、エレベーターではなく階段を使う、少し遠回りして歩くなど、小さなことから始めてみてください。
2. 脳を活性化させましょう

脳に良い刺激を与えることは、認知機能の維持に役立ちます。記憶ゲーム、計算問題、パズルなど、脳を積極的に使うトレーニングは、認知機能の維持や改善に有効です。
また、新しいことを学んだり、今まで興味があったけれど手を出せなかった趣味に挑戦したりすることは、脳に良い刺激を与え、認知機能の低下を防ぐのに役立ちます。
3. 人との交流を大切に、社会とつながりましょう

地域活動に参加したり、友人や家族と積極的に交流したりすることは、脳を刺激し、新しい神経細胞の生成を促進することで、認知症の発症リスクを減らすことにつながります。
「社会的な孤立は認知機能の低下を加速させる要因となる」とされていますので、人とのつながりを大切にしましょう。
活動的なライフスタイルは、心の健康を保ち、うつ病などのリスクも低減します。
4.食習慣の改善も大切です

バランスの取れた食事、特にカルシウム、ビタミンD、たんぱく質を適切に摂ることは、骨や筋肉の健康を支え、全身の健康維持につながります。高血圧や糖尿病などの生活習慣病をしっかり管理することも、認知症予防には欠かせません。
不安な時は早めに相談しよう

もし、物忘れなどで「いつもと違うな」と感じるような異変に気づいたら、神経内科や認知症専門医へ早めに相談するのがおすすめです。適切な治療や対応を早期で開始でき、進行を抑制するだけでなく、認知機能の維持や改善が期待できます。早期の適切な対応は、患者さん自身の生活の質(QOL)を改善することに加え、介護する人の負担も減らします。
認知症にともない興奮、妄想、徘徊、幻覚などの行動や心理症状が現れることがあります。このような場合は、まずは環境を整えたり、じっくり話を聞いたり、運動を取り入れたりする非薬物療法が基本で、必要に応じてお薬を併用します。
また、 認知機能の低下を加速させる要因として、認知症ではないのに一時的に意識が混濁する「せん妄」や、「うつ病」、意欲が低下する「アパシー」などあります。受診すれば、これらの症状にも適切に対応することが可能です。
認知症の予防には、日々の生活習慣、身体活動、知的活動、そして社会との交流を全て見直す、総合的な取り組みが不可欠です。
年齢を重ねることを恐れず、今できることに意識的に取り組むことで、健やかで豊かな人生を送りましょう。
こんにちは、健康管理士・腸内環境管理士の中谷です。三姉妹の母で、毎日にぎやかに過ごしています。楽しみは美味しいお酒と観葉植物を育てること。美酒を作る発酵の力と、植物が持つ癒しのパワーを日々実感中です。植物で大切なのは根っこですが、人間にとっての根っこは腸。腸にまつわるお話や、健やかに過ごすヒントなどをお届けします。ぜひ、ご一読いただければ幸いです。